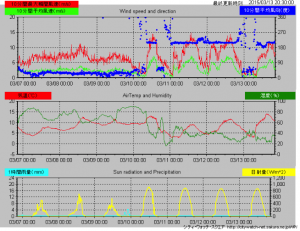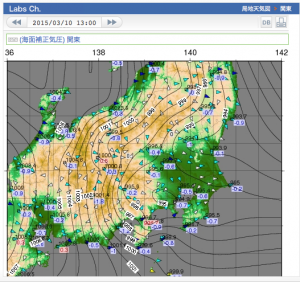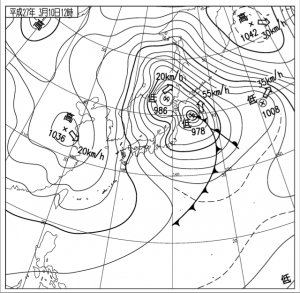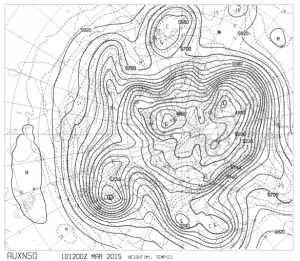地球が温暖化しているという考えは、観測と理論の両者が互いに補償し合って成立するようになった。この経緯は、近代科学の発展の歴史そのものといってよいだろう。地球環境が変わりつつあることを感じはじめていた時代に、地球温暖化曲線はそれ自身が万人の興味をそそるものであり、気候学者や気象学者にとっては曲線の質的向上が重要な研究テーマになっていた。現在では、地球温暖化曲線は今世紀末まで予測されるようになり、緩和策(温室効果ガス濃度の抑制技術の開発)や適応策(広範な生態系への影響予測・評価と対策技術の開発)の議論の基礎となっている。
地球温暖化曲線にとって、いわゆる夜明け前の時代が、フーリエ(Fourier)、チンダル(Tyndall)、アレニウス(Arrhenius)が活躍した19世紀中頃から終わりにかけてと考えてよいだろう。最初に登場するFourier(1824)は、地表面の効果を除外して地球を包む大気中に取り込まれる熱について研究し、大気の温度が太陽から地球に到達する放射エネルギーのみで計算するより高温になる(大気が存在しなければ、地球の温度はいわゆる放射平行温度(約-18℃)になるが実際には15℃に保たれている)理由について初めて議論した。この現象は温室効果に他ならない。しかし彼の研究は、確かな結論に到達しなかった。フランス語で書かれた論文は1836年にアメリカで英訳された。
その後、イギリスの物理学者Tyndall(1861)は、二酸化炭素など特別な気体が赤外線を効率的に吸収する事実を実験的に示し、フーリエの研究以降多くの科学者の興味の対象となっていた大気の熱的特性に関する問題に一つの答えを与えた。すなわち温室効果ガスの発見である。彼は、いわゆるチンダル現象を発見した人物でもある。
スエーデンの著名な物理化学者Arrhenius(1896)が、Tyndallほかの結果を使い二酸化炭素の増加に対する全球気温の感度を推定した。このように、長期の気候変動に温室効果ガス濃度の上昇が影響することが指摘された。しかし現在知られているような、人為的な化石燃料燃焼が大気中の二酸化炭素濃度上昇の原因であることにはまだ言及されていなかった。アレニウスの研究は、近年の気候変動の解明のほか氷河期のように長期に及ぶ大規模な気候変動の解明に対して、むしろ大々的に利用されたようである。これに関して、同郷の友人であるEkholm(1901)が「地質学と過去の歴史からみた気候の変動とその要因」という論文で、彼の主張の裏付けとなる重要な証拠の一つにアレニウスの考察を引用している。
しかし、大気中の二酸化炭素濃度上昇で気候が変わるという説はまだ広く知られていない時代だった。この報告の核心である地球規模の気温変動を示す曲線が世に出るのは、1938年のCallendarの論文まで待つことになる。